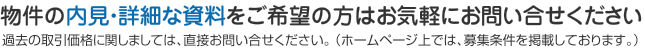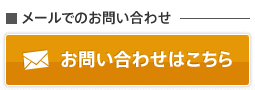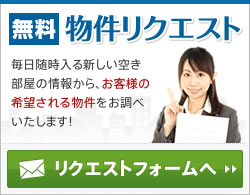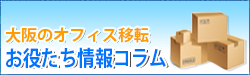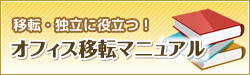オフィスの正月飾りとして用意すべきものと、飾り付ける時期

年末になると、オフィス内の正月飾りの準備を始めるようになりますが、意外と細かなルールに関してはあまり知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回はオフィスで必要な正月に用意するものと、飾り付けを行う時期についてご紹介します。
正月に用意するもの3つ
・門松
神様が空から降りてくるための目印として「門松」は生まれたと考えられており、神様を家に迎え入れるための依り代とされています。
文字どおり「門」に飾っておくことが一般的で、オフィスでは入り口に当たる部分に置くようにします。
・しめ飾り
元々は自分の家が神様をお迎えするためにふさわしい、神聖な場所であることを示す印に当たるものがこの「しめ飾り」です。
そこから現在はオフィスや家の内側は清らかな場所であることを伝えるためにしめ飾りを用意するようになりました。
オフィスでは入り口のドアの正面に吊るすことが一般的です。
・鏡餅
鏡餅は部屋の中でも皆が集まる場所に飾ります。
三方という台を用意し、半紙を敷いて昆布やゆずり葉を乗せて餅を重ねます。その上には「橙(だいだい)」と呼ばれるミカン科の木の実を乗せることが正式な鏡餅の飾り方です。
「みかん」のイメージがある方が多いと思いますが、正しく鏡餅を飾る際は、橙を用意するようにしましょう。
橙はその名前から「代々栄える」という縁起もののため、忘れずに用意したいものです。
正月飾りを飾る時期は?

飾り付けを行う時期は「松の内」に行うべきとされています。
「松の内」は地域によって期間は異なりますが、元日から1月15日前後の期間を指すことが多く、それに合わせてオフィスで飾り付けを行うことが一般的です。
現代の日本では「クリスマスが終わった後から」という認識が強く、12月26日ごろから飾り付けを始めます。
縁起物のため遅くても28日、30日までには飾り付けるようにしましょう。
・正月飾りで忘れてはいけないタブー
12月29日と12月31日に正月飾りを行うことはタブーとされています。
29日は「苦待つ」といわれており縁起が悪いとされており、31日は「一夜飾り」といい、神様に対して誠意がないとされるため良くないと考えられています。
このため正月飾りを行う場合は28日まで、遅くとも30日という考えが一般的になっています。
正月飾りを片付ける時期は?
鏡餅に関しては「鏡開き」の時に片付けることが一般的ですが、正月飾りは前述した「松の内」の期間が終わったら片付けるようにします。
片付けたものは神社に納めてどんど焼きによって処分を行っていきます。
来年も良い仕事ができるように、このような正月飾りは正しく行っていきたいものです。
時期を正しく守って、気持ちよく来年を迎えられるようにしましょう。